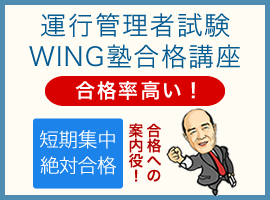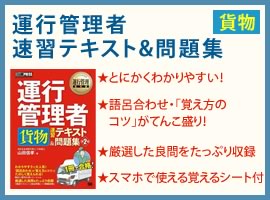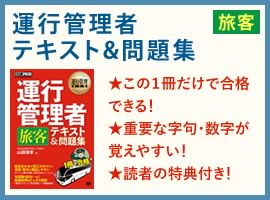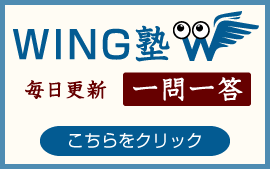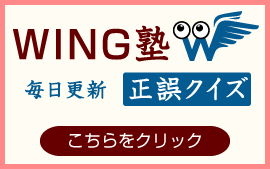2026年1月18日
≪誤り問題≫ 30選の解答
〇貨物自動車運送事業法
- 事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の「認可」を受けなければならない。
- 事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の「認可」を受けなければならない。
- 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務「時間」及び乗務「時間」を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
- 「業務前」の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
- 事業者は、法令の規定により運行指示書作成した場合には、当該運行指示書を、「運行の終了の日」から1年間保存しなければならない。
- 事業者は、車両総重量が「8トン」又は最大積載量が「5トン」以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した運転者に対し、貨物の積載状況を「業務の記録」に記録させなければならない。
- 事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、「当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後 1ヵ月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りではない。」
- 次の事案については、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣へ報告を要するものである。事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が「0.5メートル」の畑に転落した。
〇道路運送車両法
- 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から「15日以内」に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
- 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、当該自動車に自動車検査証を「備え付けていなくても、これを運行の用に供することができる。」
- 初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であって、車両総重量8トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期間は「2年」である。
- 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が「7トン」以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
〇道路交通法
- 駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(「貨物の積卸し」のための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- 車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、「歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないように」しなければならない。
- 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から「3メートル以内」の道路の部分においては、駐車してはならない。
- 警察官は、過積載をしている車両の運転者及び使用者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
- 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、「一時停止し、または徐行して、その歩行を妨げないように」しなければならない。
〇労働基準法
- 法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
- 「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の「総日数」で除した金額をいう。
- 使用者は、貸切バス運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が「14時間」を超える回数は、1週間について2回までが目安とすること。
- 使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1ヵ月について284時間以内で、かつ、1年の拘束時間は、3,300時間を超えないこと。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1ヵ月の拘束時間を「310時間」まで延長することができる。
- 休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続「9時間」を下回ってはならない。
- 使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備があるときは、1日についての最大拘束時間を「20時間」まで延長することができる。
〇実務上の知識及び能力
- 自動車がカーブを走行するとき、自動車の重量及びカーブの半径が同一の場合には、速度が2倍になると遠心力の大きさも「4倍」になることから、カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導する必要がある。
- 他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識を持って、自車の速度と「停止距離」に留意し、前車との追突等の危険が発生した場合でも安全に停止できるような「速度または車間距離」を保って運転するよう指導している。
- 前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見え方が異なり、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に「余裕がある」ように感じ、乗用車の場合は車間距離に「余裕がない」ように感じやすくなる。したがって、運転者に対して、運転する自動車による車間距離の見え方の違いに注意して、適正な車間距離をとるよう指導する必要がある。
- 適性診断は、運転者の運転能力、運転態度及び性格等を客観的に把握し、運転の適性を判定することにより、「運転者自身の安全意識を向上させるためのもの」であり、ヒューマンエラーによる交通事故の発生を未然に防止するための有効な手段となっている。
- 運行管理者は、業務開始及び業務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等は、「運行上やむを得ない場合に、該当しないため、電話その他の方法による点呼はできない。」
- 業務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し道路交通法施行令で定める呼気1リットル当たり15ミリグラム以上であるか否かを「判定するためのものではない。」
- 事業者は、深夜(夜11時出庫)を中心とした業務に常時従事する運転者に対し、法令に定める定期健康診断を「6ヵ月以内ごと」に1回、必ず、定期的に受診させるようにしている。
≪穴埋め問題≫ 30選の 解答
〇貨物自動車運送業法
- あらかじめ
- 2ヵ月
- 助言、指導
- 5,24時間
- 7,4
- 15,20
- 30
- 事業者
〇道路運送車両法
- 15日、移転
- 自動車検査証、検査標章
- 1.8
- 200
〇道路交通法
- 軽車両
- 進行妨害
- 5
- 徐行
- 準中型自動車
〇労働基準法
- 30日間、30日間
- 14日
- 45分、1時間
- 44時間
- 10分
- 3時間
〇実務上の知識及び能力
- 2
- 制動距離
- フェード
- 4
- 衝突被害軽減ブレーキ
- 10
- 3分の2